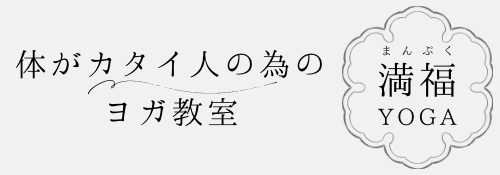こんにちは。
- 勤めている会社の賃金が安い。
- 今の仕事内容では将来が不安。
- 一定の収入を得ながらも、何か新しいスキルを学びたい。
こういった理由で副業・兼業を希望する人は年々増加傾向。
2020年は在宅時間が増えて、その傾向は更に高まったと言えるでしょう。
今回は、
- 「今後の日本の働き方はどのように改革されていくのか?」
- 「副業・兼業のメリット・デメリット」
を話題にしてみたいと思います。
目次
『正社員でも副業・兼業』の時代がくる。
今まで私の中で、社員の副業・兼業は禁止されているイメージがありました。
かと言って、Wワークしている人はゼロではなく、会社に報告せずにこっそりやるモノというイメージ。
私自身も、収入に不安を抱えていた時は平日会社に行き、週末アルバイトをした経験があります。
体力的にはかなりハードでした。幸い本業の方が忙しくなったので2年程でアルバイトは卒業しました。
Wワークの事は会社の人には言えず、若干後ろめたい気持ちで働いていました。
ところが、この働く常識・暗黙のルールが厚生労働省の働き方改革により、変化しつつあります。
国が推奨する副業・兼業
①副業・兼業の促進に関するガイドライン。
厚生労働省は、副業・兼業を希望する人が、安心して取り組むことができるよう、労働時間管理や健康管理等についてガイドラインを作成しています。
- 2017年3月、「働き方改革実行計画」 を踏まえ、副業・兼業の普及促進を図ることが決定(働き方改革実現会議)。
- 2018年1月、副業・兼業について、企業や働く方が現行の法令のもとでどういう事項に留意すべきかをまとめたガイドラインを作成。
- 2020年9月、企業も働く方も安心して副業・兼業を行うことができるようルールを明確化するためにガイドライン改定。
このガイドラインには・・・
「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由である。」
とあります。
しかし、以下のケースに該当する場合は、各企業がそれを制限することが許されます。
- 労務提供上の支障がある場合
- 業務上の秘密が漏洩する場合
- 競業により自社の利益が害される場合
- 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
ガイドライン内では他にも企業側・労働者側双方の立場で副業・兼業のメリットデメリットが記載されており、
企業側に対しては・・・
基本的な考え方として「原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当である。」と述べています。
特に副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業に対して、
その行為が業務に支障をもたらすものかを今一度精査し、そうでなければ労働時間外については、希望に応じて副業・兼業を認める方向で検討するよう求めています。
労働者に対しては・・・
- 自身の会社が定めるルールに則って、業務内容・就業時間が適切な副業・兼業を選択すること。
- 副業・兼業を行うに当たっては、過労により健康を害したり、本業務に支障を来たす事がないよう、労働者自らの業務量・労働時間・健康状態を管理すること。
- 労働者と企業の双方が納得感を持って進める為に、双方間で十分にコミュニケーションをとること。
を求める内容になっています。
②モデル就業規則の改定。
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」改定に伴い、モデル就業規則も改定されました。
- 2018年1月、労働者遵守事項の「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」という規定は削除。副業・兼業についての規定を新設。
- 2020年9月、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」改定に伴い、副業・兼業についての記述をさらに改訂(第14章第68条)。
主に、前項で記載したガイドラインと同じ内容が書かれています。
ですが、これはあくまでもモデル規定であり、現実の就業規則内容は各事業が定めるもの。
モデル就業規則には「副業・兼業に係る相談、自己申告等を行ったことにより不利益な取扱いをすることはできません。」と記載されていますが、
実際は、堂々と胸を張って副業申請ができる会社はまだ数少ないのが現実です。
副業・兼業OKの会社が増える理由。
行政が副業・兼業を推奨する流れに舵を切っている事も根拠の一つですが、
「今後そんな会社が増えていく、正社員でも副業が普通に認められる時代が来る。」と思える訳があります。
なぜなら・・・
優秀・多彩な人材は副業OKな会社で働きたい。
厚生労働省のガイドラインに細かく書いてありますが、副業・兼業には労働者と企業双方にメリットがあります。
【労働者の メリット】
- 離職せずとも別の仕事に就くことができ、スキルや経験を得る事で主体的にキャリア形成ができる。
- 所得増加。
- 所得を活かして、自分がやりたい事に挑戦でき、自己実現可能。
- 収入を得つつ、よりリスクのない形で将来の起業・転職に向けた試行ができる。
【企業のメリット】
- 労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。
- 労働者の自律性・自主性を促す。
- 優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力向上。
- 労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会の発展に繋がる。
つまり、会社の業務外にも興味を持ち、自主的に勉強してスキルアップを望む主体性のある人にとっては、
収入面においても、個人のキャリア形成においても、副業の選択肢がある環境で働く方が絶対的にメリットが大きいのです。
会社に黙ってコソコソWワークするより、働き方を相談できる環境の方が安心できますよね。
そうなると、優秀でお金を稼ぐ能力のある人材は自然と副業・兼業を許可している企業に流れます。
企業にとっても、自社で一から教育しなくても、他で学んだ知識や能力を発揮してくれる人材を採用できればその方がプラスです。
例えば、一時的に会社の経営が傾いて、十分なシフト・賃金を従業員に与えられなくなったとしても、副業という選択肢があれば、従業員の生活水準は保たれ、人材の流出を防ぐ事ができます。
世間一般的に副業OKの会社が増えれば増えるほど、優秀人材獲得の為には多様な働き方を許容するルールに変えざるを得ないのではないでしょうか?
私が経営者なら、全て教育しなくても、自分で勝手に学んで成長してくれる人を雇いたいです。
正社員しながら副業・兼業の難しさ。
ここまで副業・兼業のメリットについて主に書いてきましたが、
ここからは、仕事を両立させるのがいかに難しいかというデメリットを書きます。
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、その留意点について以下のように書かれています。
労働時間や健康管理への対応、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務をどう確保するかという懸念への対応が必要。
・労働時間・健康管理・職務専念の義務を果たせるか?
副業・兼業で一番難しいのは自分の時間と健康の管理だと思います。
正社員であれば、だいだい週5日・一日8時間程度の労働が最低条件になります。
これ以外の時間を更に別の仕事に充てるとなると、休息や趣味の時間、家族との時間を削る事になります。
心身共に健康な状態で従事するためには、高い自己管理能力が必要ですし、プライベートな時間がかなり失われます。
でもこれができないと、職務専念の義務が果たせません。
本業に身が入っていない事を悟られ、信頼を失い、昇格が遅れてしまったら、かえってキャリアの足を引っ張ってしまいます。
安易に副業・兼業を始める前に、『自分が今頑張るべき事・集中するべき事は何か?』を見極めて判断できることが前提になります。
・秘密保持・競業避止の義務を守れるか?
これは難しいというより、当人の倫理・モラルの話です。
当たり前ですが、企業にとってライバルへの情報流出は大きな損失なので、同業種での副業はできないと考えた方がいいでしょう。
競合の会社に加担するような仕事も、同様に許可は下りないでしょう。
会社が副業を快くOKにするには、双方の信頼関係が重要で、互いのWIN-WINが成立していないと副業は歓迎されないのです。
まとめ
以上の事を踏まえて現状をまとめると、
- 副業・兼業にはキャリア形成や副収入のメリットがあり、国もその働き方を推奨しはじめている。
- 現状は副業を公に認める会社はまだまだ数少ないが、将来増える可能性は大きい。
- 本業との両立には高い自己管理能力・最低限のモラルを要し、プライベート時間の損失は避けられない。
こんな感じでしょうか。
私も副業経験者なので、軽い気持ちでおすすめはしませんが、長い職業人生の中で色々な仕事を経験しておく事は学びになります。
体力的に若い時しかできない職種もありますし、定年退職してからでは体験できない仕事も沢山あります。
個人的な意見を言うと、理想的な副業の形はやはり
『自分の将来のキャリアに繋がる何か』
だと思います。
収入重視だと、時給の高いアルバイトを選びがちですが、その時間は使い捨てなので“いい経験”になって流れて終わってしまいます。
今回コロナで世の中の働き方が大きく変わってしまったように、自分の仕事の需要がいきなり無くなる日がくるかもしれません。
そんな時に、複数の働き口・人脈・経験があれば焦らずに対応できますよね。
ぜひそういった切り口で、副業を始めてみませんか?
自分で働く時間が無い人は、「お金に働いてもらう」という方法もありますので、興味があればこちらの記事も是非ご覧ください!